 日々雑感
日々雑感 不惑になって思うこと。地域のNPOと共に過ごした30代
先日、不惑になりました。不惑というけれど、惑いまくりの毎日ですw 40歳になって思うのは、あれ、いい年のおっさんになったのに大したことないぞ、と。子どもの頃、40 歳 といったら「ザ・大人」で憧れる存在だったのに自分がなってみると毎日頭を抱...
 日々雑感
日々雑感  日々雑感
日々雑感 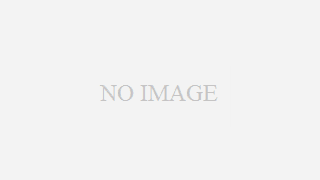 日々雑感
日々雑感 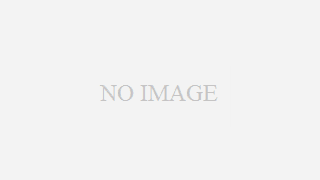 日々雑感
日々雑感 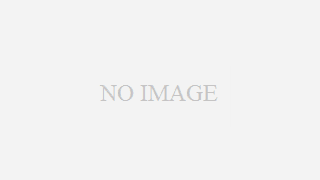 日々雑感
日々雑感 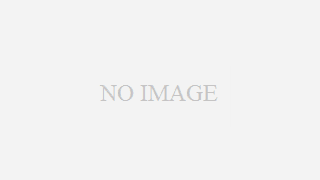 日々雑感
日々雑感 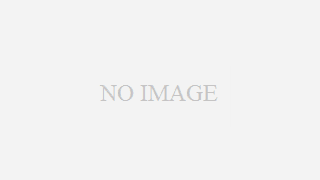 日々雑感
日々雑感